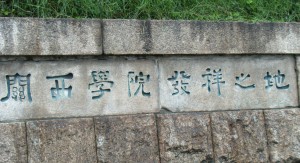2011.10.16
合格おめでとうございます !
嬉しいよりもホッとした・・・
今年は受験者数が偏っていたり、少なかったりで、意外な結果も出たようです。早くから取り組んでいた方はほとんど合格したとは思いますが、やはり結果を聞くまでは安心できないのか、「合格」を頂いた時は嬉しいよりも「ホッとした」というのが実感のようです。京都はこれからになりますし、国立を再度挑まれる方はまだまだ先が長い道のりですね。プロゲートでも合格者の声をぞくぞく頂いております。まだこれからの方もおられますが、合格された方には「おめでとうございます」そして「お疲れさまでした」
来年の受験生は今年の倍近くになります。今の年中さんはそのあたりを十分に意識して残り1年を送って下さい。
現在の合格校
追手門・城星・賢明・近畿大附・関学・仁川・四天王寺・小林聖心
2011.10.12
小学受験に乗馬・・・?
関西の小学受験に乗馬合宿は必要・・・?
お母さんからの質問にこんなお話がありました。
「この夏に小学受験に向けて入塾しようとしたら、乗馬合宿と夏の講習会、合わせて50万も要求されました。」そればかりか
「授業料も2時間で1回3万円」と言われたそうです。
しかも、「授業でやったプリントも回収、宿題もない、いったい何をやっているのか分からない・・・」
「これって本当に必要なんですか・・・?」
本当に首を大きく横にかしげたくなるようなお話です。正直言って、小学受験に直接乗馬は必要ないと思います。「馬と触れ合うと子供は変わる」という触れ込みですが、「だから何なんですか? 」と言いたくなりませんか・・・・
自然と触れ合う、動物と触れ合う、こういう分野は各ご家庭での個別の体験の範囲であって、決して塾でやるべき内容ではないと思いますが、どう思われますか・・・
それに、費用面はさておき、授業で何をやっているか分からない、宿題がない、これは大きな問題だと思います。親の指導が必須な内容がたくさんあるのに、これでは何をどうしたらいいのか全くわからないのではないでしょうか・・・・
そんなご縁から、私どものプロ家庭教師の先生が指導に行くことになりましたが、
「先生がどうやって教えるのかをそばで見る事が出来るので、先生が帰った後でも同じように子供に教えられるので、塾の3倍も6倍も成果が出るし、先生に色々と相談できるし、子供の出来不出来が本当につぶさにわかるので、本当に感謝しています。初めからお願いしておけば良かった。しかも、費用面でも安くつくし・・・」
とおっしゃっていただきました。
これがご縁で、受験後も継続して指導に行くことになりました。今後は中学受験に向けての土台作りをしっかりとやっていく予定です。
2011.09.12
塾から見放され・・・
東大寺は意地でも合格させたい
6年生のこの時期に東大寺クラスに入れなかった。ただ、よくよく分析すると3科目の合計のクラス分けで、本人は社会が得意なので十分に勝負できるはず。機械的に塾の規定で外されたとしても、東大寺は4科目均等配点の学校なので十分にチャンスはある。こうなったら、絶対に意地でも合格させたいと思います。今からでも理科や社会はもっと伸びます。頑張って国語の悪い分をカバーできるように指導します。昨年も塾から見放された生徒を合格させました。絶対に挽回出来る要素はあります。
S講師
2011.09.12
甲陽の理科は今からが勝負
あと4カ月あれば対応できます
灘にするか甲陽にするかを迷っている人がいると思いますが、少なくとも今月中には決めないと、理科の観点からすると、間に合わなくなります。灘の理科は説明文が長いけれど問題自体はそんなに難しくないので、コツコツと過去問をやって慣れれば何とかなると思います、ただ甲陽の理科は計算が難しいので、いまからスタートしないと間に合いません。文章の式が書けるかどうかで随分時間が変わってきます。なにしろ甲陽の理科は灘よりも難しいので、十分に時間を割いて取り組ませたいと思っています。
O講師
2011.08.25
蝉が鳴いています・・・!
虫籠に蝉 ?
最近はビルの立ち並ぶオフィス街でも蝉の鳴き声が聞こえるところもあります。先日もマンション住まいの方がお父さんと網と籠をもって蝉取りをしている様子を見かけました。籠の中には何匹も蝉が入っていて、ジージーと大きな声で鳴いていました。それを持ってエレベーターに乗って帰りました。以前はどこにでも見かけるシーンでしたが最近はあまり見かけなくなりました。地域にもよるのかもしれません。
夏休みの自由研究でよく昆虫採集をしていた時代も思い出されます。特に男の子は昆虫に興味を持つ子供が多いので、カブトムシや鈴虫、ザリガニを飼っているご家庭も数多くあります。中にはちゃんと餌を与えて長生きしている場合もあるようですが、悲しいかな途中でほったらかして死なせてしまうケースが多いようです。ちゃんと飼ってその観察をするのであれば大いに奨励したいと思いますが、そうでなければあまり感心できません。やはり採取したのであれば親が飼い方を教えてあげるとか、本人に調べさせるという指導がなければ子供にだけ任せておいては昆虫もかわいそうです。
蝉はうるさいほど泣いていて比較的簡単に居場所も分かり、採取しやすいと思います。何匹もいるので少々採取してもいいだろうと簡単に思いますが、蝉の寿命はほんのわずか。あっという間に死んでしまいます。道を歩いていても蝉の死骸がゴロゴロしています。それを見ると「あの鳴き声は断末魔の叫び」のようにも思えてしまいます。そう考えると、蝉は飼うものではない昆虫の一つだと思います。標本として一匹とるのはいいとしても、何匹も虫籠に入れておくのはどうなのでしょうか・・・・
むしろ、「蝉は寿命が短いから・・・」と言って子供に教えてあげる方がいい教育になるように思いますが・・・・
そんな中から生き物を飼う責任感を持たせ、命の重要性を教える事が親子の会話の中にも大きなプラスになっていくと思います。
本物を見せる
昆虫だけではなく動植物に、日頃はプリントや写真でしか触れていない子供も多いようです。このお盆の時期は塾もお休みの時期なので、家族で旅行にも行かれると思います。こういう機会に大いに本物に触れてほしいですね。プリントや写真で姿かたちは分かっても、その触感や匂いは分かりません。どれだけ文明が発展しても触感や匂いを伝える事は出来ません。(匂いの出るテレビが出来ればノーベル賞・・・・?)
出来る範囲で散策をして自然に触れ合い、子供との会話を楽しんで下さい。日頃とは違う一面が発見できるかもしれません。
2011.08.10
最終的には自分で確認を・・・
受験校の決定は直接見て聞いて!
あと受験まで1カ月半。受験生は最後の追い込みで夏期講習に追われている毎日ですね。
今年は学校によっては定員を確保するのが難しくなる見通しの学校が、昨年よりも増えそうな気配です。そういう最近の情勢からか、以前は子供の成績で行ける学校を決定していたものが、子供に合う学校をより慎重に選ぶ傾向に変わってきているような気がします。
先日も学校説明会に行かれた方が、「去年と学校長が変わって方針が変わったから、ここの学校は合わない」とか「今までいた●●●先生が違う学校に変わったから、そちらの学校に変えます」とか「やたら進学先ばかりを強調されるからちょっと・・・・」などと様々な声が上がっています。また「いい学校は先生方が笑顔で生き生きしていますね!」とおっしゃる方もおられます。それだけ皆さんが塾からの情報だけに頼らず、自分自身で足を運び、目で見て、耳で聞いて判断をする傾向が強くなってきているという事かも知れません。
今までは学校側が生徒を選ぶ時代でしたが、これからは各ご家庭が学校を選ぶ時代という風潮が強くなっていくのかもしれません。
合否の決め手はペーパーテストよりも行動・面接
学校側は今までは学力が高く総合評価も高い、という生徒を優先していましたが、少子化という問題もあり、兄弟関係、内部進学、関係の深い塾からの推薦などでの入学がより安心しての受験になっています。学校として今一番警戒しているのは、学校に対して批判的な方、悪影響を及ぼすような子供、要望の多い親などの見極めです。その見極めとして一番にあげているのが、子供の指示行動、面接、口頭試問です。だいたい子供をみれば親が分かりますし、逆に親を見ても子供も分かります。ただその当りはペーパーテスト等の点数では分かりません。ですから、余計にそういう前述の内容を重視しているのです。特にお行儀の悪い子は目にとまります。これは集団時の行動だけではなく、それぞれのテストの中でもちゃんと指示が聞けて従っているかなどからも分かります。ですから今後入試まで、また年中、年少の方もその点に注意しながら日々取り組んでいってほしいと思います。年長さんぐらいになるとかなり差が付いていますから、出来れば年中、年少の時期から特にお行儀面を重視して育ててほしいと思います。
2011.07.27
算数嫌いの原因は低学年にあり
計算は速いだけでは意味がない
子供は足し算より引き算、掛け算より割り算が苦手です。これに小数・分数が加わるともっと出来なくなる子供が増えます。実はこれは練習不足と一言では片付けられない事です。よく公文やそろばんをやって計算スピードが速い子供がいますが、4年・5年生ぐらいになると、だんだんとミスが増えてきたり、解けなくなったりします。これは何が原因かというと、単純に計算のやり方だけを習得しているからです。それでは複雑で長い計算は出来なくなります。
例えば
9×5+9=
これをどう計算していますか・・・? おそらく前から順番に計算して、
45+9=
としていませんか・・・? これがただ単に計算しているということです。これを
9×6=
とするのが計算の工夫であり、考える習慣をつけるということになるのです。
9×5-9=
これは
9×4=
計算は常に工夫をしようという意識を持たせることが必要です。でないと
323+324+325+326+327+328+329+330+331+332+333=
99×75+124×78+124×21=
こんな問題をまともに順番に計算していては逆に時間がかかり計算ミスが起きます。
単位の概念をつけて活用する
算数嫌いの多くは単位・少数・分数・文章題でつまずいています。これも理屈が分かっていないのと概念がないからです。例えば1分が60秒は分かっていても、1秒は60分の1秒が言えなかったり、長さの単位、重さの単位、量の単位など様々な単位の関係がイメージ出来ていないのが原因で算数嫌いになっています。色々な単位を習った時点で、その単位が実際どれぐらいのものかを実感させる事があまり出来ていないようなので、親としては生活の中でもそうした単位を実感させるような工夫を考えてほしいものです。それとともに、例えば3時は90度、1時は30度、1分は6度、などと重ね合わせて勉強する事も大切です。これは3年生レベルです。
2011.07.25
中1なのにもう差がついています
難関校ほど進度と内容が深い
中1だから中1の内容というものではありません。各学校での方針があるので、使用している教材も違う、進度も違う、内容も違う、教え方も違う、当たり前のことです。中1なのに高校受験レベルの内容をやっている、中1なのに高校の内容をやっている、そんな学校は難関校ほど多いのです。例えば、普通、英語はこの時期はまだまだ単語と簡単な文だと思います。まだ筆記体で書けない生徒もいます。かたや洛南のように、hasやhaveを習っている。使っている教材も最上級のテキストです。また数学においても、普通は正の数負の数・方程式ですが、難関校は早くも不等式や高校受験レベルの幾何です。使用教材も発展レベルの教材です。
中には教材を使わずにすべて先生のプリントで授業をしている学校もあります。授業の進み方も、解説、説明が多く、その演習は「やっておくように!」で終わり。授業時間内でわざわざ練習問題に時間を取るような事が少ないのが現実です。ですから当然宿題も多いですし、教科によっては予習をしておかなければついていけないのは当然。ですから、この1学期の間にしっかりと勉強したかしていないかで差がつくのは当然です。
考え方としては中3までの内容を学年に関係なく進んでいる、と考えてもいいかもしれません。中には高校レベルの内容をやっている学校もあるくらいですから。
数学や英語だけではありません
数学や英語の内容もかなり高度ですが、案外意識していない物理や化学も難しいことをやっています。専門用語がどんどん入ってきていて、それをすぐに覚えていないと、計算が出来ないという、とんでもない世界です。中学受験で勉強している内容はすべて出来ているという前提で進んでいます。これらをすべて学年平均、またはそれ以上を狙うのであれば、そうとう勉強量が必要です。
そんな中、もう塾に行っている生徒もいますが、学校の内容だけでも相当な時間が必要なのに、よくそれ以上の課題をこなしているものだと感心します。ただそれで結果が伴っているかどうかは別問題ですが・・・・
今の時期はまだ学校の内容についていくことが最優先な時期。学校からも、塾や予備校には行かないで下さい、と言われているはずです。言われなくても、学校の進度が速いだけにそれ以上この時点でプラスする事は疑問です。むしろ学校の授業内容を完全に理解し、その内容を深めていくのに時間をかけるべきです。とは言っても相当な内容量がありますから、この時期に1学期の総復習と宿題をきちっとやって欲しいところです。
2011.07.11
合格第1号
早くも合格通知
編入学試験で合格しました。学校名は公表できませんが、無事に合格出来て良かったです。お母さんもほっと一安心です。募集も若干名だったので心配されていましたが、結果的にはペーパーテストでも高得点でした。また、運動や面接もそつなくこなし、見事合格。夏休み後には新しい学校生活が待っています。しばらく慣れるのに時間はかかると思いますが、頑張って下さい。
N講師